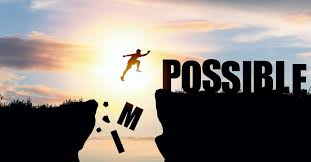こんにちは、飲食店コンサルタントのキミタです!
皆さんは「このまま飲食店で働いてていいのかな・・・」なんて疑問を感じたことありますか?
もちろん、飲食が好きで働いている方が多数かと思いますし、働いている内に考え方が変わった方もいらっしゃると思います。
今回はそんな悩みを解消できる記事になればと思います!
ぜひ最後までお付き合いください!
飲食店事情

飲食店で働く人はどのような気持ちで働こうとしているのか。見ていきましょう。
得られる知識や技術
【調査概要】
◆調査期間:2015年10月22日〜2015年10月27日
◆調査対象:求人@飲食店.COMを利用している20〜30代の正社員希望者(有効回答人数:157名)
※アンケート回答者の75%が飲食経験「4年以上」うち30%が飲食経験「10年以上」。経験豊富なユーザーが中心でした。
このレポートのポイント
- 飲食の仕事を選ぶ一番の理由は、人に喜んでもらえる、専門技術を身につけられる!
- 20代はチームワークも重視する!
- 30代は起業(独立)しやすいことも大きな動機!
20~30代が飲食の仕事を選ぶ理由

ついで「起業(独立)しやすい」「学歴に関係なく活躍できる」がともに3割を占めました。これらは、キャリアプランに独立を掲げる人が多い、現場を重視する、という飲食ならではの結果といえます。
その他の声としては、「身内に腕前を披露できる」「とにかく飲食業が好き」「昔から料理が好き」などがありました。
20代が飲食の仕事を選ぶ理由

なお、30代に比べて「チームワークを重視して働きたい」「ライフスタイルに合わせて働きたい」という回答も多数。若い人ほど仲間意識が強く、仕事とプライベートのバランスを重視したい、という傾向がみられました。20代を採用したい場合は、研修制度や身に付くスキルをアピールする、チームワークの良さやフラットな職場環境をアピールする、また、勤務時間や休日を選べる柔軟な勤務スタイルを作るのも有効的な方法と言えますね。
30代が飲食の仕事を選ぶ理由

ついで「起業(独立)しやすい」が34%と多く、将来のキャリアプランが明確になってきている30代では、独立しやすいことを飲食業界で働くメリットととらえている人が多いようです。
また、「学歴に関係なく活躍できる」「出世が早い(昇給・昇格が早い)」ことを理由にする人も20代に比べて多数。これらは他の業界と異なる飲食業界の特性といえます。30代を採用したい場合は、独立支援制度を設ける、技術向上のための環境をアピールする、または昇給・昇格について詳しく記載するのも有効的な方法と言えますね。
働いている人が抱く悩み

20代や30代で就職し、抱える悩みが「その後のこと」だと思います。
現場職では店舗で労働することが一番求められます。人件費や教育、指導、組織構築など様々な事を少数で行っているためです。飲食企業の多くは店が資本なため店舗を中心とした経営が求められています。上手にキャリアアップができれば問題ないですが、多くは店長で店に出ずっぱりになっていることが多いのではないでしょうか?
そんな中でこれから先もずっと長時間の労働や身体を使って労働をしていくのか。悩んでいる部分も多いと思います。若い頃は問題ないですが、年齢とともに身体は衰えてくるものです。今後とはその先のポストも含めて根詰まりが起きている事が現場一生になっている要因かも知れません。
合わせてその他の悩みも見てみましょう。
飲食店が抱える労働環境の問題点
飲食業界は「残業が多い」「休みが不定期」など労働環境が劣悪で退職者が多いことが問題となっています。それらは業界ならではの特徴ともいえますが、働く人にとっては退職を考える引き金になることもあるでしょう。飲食業界がかかえる労働環境の問題点の詳細とそれぞれの改善方法についてみていきます。
長時間勤務

飲食店で働く人が辛くなる要因のひとつは「長時間労働」です。正社員であれば一日あたり10時間労働はめずらしくありません。
飲食店での仕事が長くなる原因は、仕込みや清掃などの開店準備、閉店後の閉め作業に時間がかかるということがあります。
営業時間中に働く時間は通常だとしても、前後の開店準備と閉店準備に時間がかかりますので、結局は毎日残業になったりします。
長時間労働を断ち切るためのポイントは開店・閉店作業が効率化できるかどうかです。
営業時間の前後の仕事を効率化することができれば働きやすくなります。働きやすくなれば、人手確保もしやすくなりますので、慢性人手不足から解消され、よい循環に持ち込むこともできるでしょう。
システムの導入や、外部委託を取り入れなどで効率化を図り働きやすい職場にすることで、労働環境が大きく改善することがあります。
不規則な休み
飲食店の労働環境で問題になることのひとつは、休みについてです。
週休1日というケースや、土日祝日、年末年始に休みがとれない。などがあげられます。
それ以外にも、お店のタイプによって繁忙期があったり、イベントなどの状況で定期的に休みをとるのが難しいというケースもあるでしょう。
もちろん、冠婚葬祭など必要に応じて申し出をすれば土日祝日などに休むことは不可能ではありません。しかし、基本、繁忙期にあたる時期に休みをとるのは簡単ではなく肩身が狭いものです。
雇用者サイドが、スタッフが休みやすい環境造りをし、家庭の事情やそれぞれの状況を考慮して、平等に休みが回るように考える必要があります。
慢性的な人手不足

長時間労働と不規則な休みを理由に仕事を辞める人が多いため、飲食店では慢性人手不足というところが多くみられます。
特に、アルバイトスタッフは、まえぶれなく辞めることがあるため、飲食店は人員補充に常に追われることになります。
アルバイトスタッフが、急に辞めてしまえばその穴は残ったスタッフで埋めることになりますが、その役目は大抵、正社員が担うことになるでしょう。
そうなれば、長時間労働・休みがない→アルバイトスタッフの退職→正社員はさらに長時間労働で休みが削られる。というマイナスのループにはまってしまいます。
マイナスループを断ち切るには、根本原因である労働環境を見直して、離職率を下げる必要があります。
人材が定着しにくい
人材の定着率の低さに頭を悩ます飲食店が多い傾向です。
慢性的な人手不足であることから、採用した人材は経験のあるなしに関わらず即戦力として現場に立つことになります。採用された人にしてみれば、慣れない職場でちゃんとした教育を受けられぬまま仕事を任せられることになり、不安で右往左往しながら気持ちが萎えてしまうこともあるでしょう。負荷が大きすぎると感じると、すぐに辞めてしまうことになります。これもまたマイナスループとなっていきます。
短時間で人が入れ替わるのを防ぐためには、しっかりとした研修期間が不可欠です。職場に慣れるための時間と、仕事を理解してもらうための研修制度が行き届いていれば、人材定着率は格段に高くなります。
採用したスタッフに継続して働いてもらうためには、急がば回れ。しっかり研修をして人材育成に力を入れることで、新人スタッフの定着率があがり、結果、正社員や既存スタッフの定着率アップにもつながります。
結果として正社員の負担が増える

飲食店の仕事は人材ありきで成り立っています。調理スタッフや、ホールスタッフなどメインスタッフはテレワークというわけにはいきません。また、人員が足らないからといって、その仕事をカットすることもできません。
アルバイトスタッフなどが急にやめてしまえば、その穴埋めが必要になり、その役目は正社員にまわってくることがほとんどです。
穴埋めを任された正社員は、断ることができず、残業や休日の変更または、休日出勤を余儀なくされます。そんなことが日常的におこっていれば、正社員であっても退職を考えてしまうことになるでしょう。
正社員の誰かが退職すれば、その穴埋めは残っているほかの正社員にまわってきます。そしてその正社員も辞める。負の連鎖でスタッフの誰もが追い詰められるのは目に見えています。
そうなれば、飲食の提供という本業よりも、スタッフの手当に追われることになる悪循環になってしまします。
最近は労働環境の改善が積極的に行われている
日本全体の流れとして、業界を問わず労働環境は改善される方向に動いています。
飲食業界もその流れにのって、積極的に労働環境改善に取り組む店舗もみられるようになりました。
とは言うものの、一部の大型チェーンの飲食店など以外はまだまだ「遅れている」のが現実です。特に中堅、個人の飲食店であれば、オーナーの考え方によるところが大きく、労働環境に歴然とした差がみられます。
また、日々の仕事に追われてそれどころでない店舗もまだまだ見られます。そこで働くスタッフは、対処に困っている人が少なくないようです。
そんなことから、当組合には飲食店で働くみなさんからのご相談を多数受けています。
労働環境については、自分一人で悩んでいても前には進みません。まずは、身近な人や専門知識のあるところに相談し、解決が可能かどうかを探ってみるとよいでしょう。
長時間労働による身体の影響は非常に大きい
長時間労働は単純に「働くのがしんどい」という問題ではありません。キャパシティを超えた仕事量は心身に大きな影響を与え、重い病気などにつながっていくこともあるのです。
「まだがんばれるから」と無理をしていると、人生をゆるがす心身トラブルをひきおこすことがあります。
こちらでは、長時間労働者の健康ガイド(独立行政法人労働安全衛生総合研究所)を元に、長時間労働が体に与える負担と影響についてみていきます。
睡眠・休息時間の不足

長時間労働は、労働の負荷を大きくするだけでなく、睡眠・ 休養時間、家庭生活・余暇時間の不足を引き起こして、疲労を蓄積させます。
一日の時間は限られているのですから、労働時間が長くなればその分、休息時間やプライベートに当てる時間は短くなります。そうなれば、実質の睡眠時間が短くなったり、リフレッシュするための時間が削られるのですから、労働で溜まった疲労を回復する余裕がありません。
また、長時間労働が課せられる根本には、仕事量が多すぎたり、高度な質を要求する仕事であったりで、結果、仕事に追われて気持ちと体を休めることができないとなっています。
負荷の多い仕事はより疲労度が高いといえますので、上手に解消していかなければ、疲労が蓄積してしまうでしょう。
睡眠・休息時間が短いと作業効率が下がり、注意力も低下しますので事故やケガを引き起こす原因になるという問題があります。
疲労の蓄積
長時間労働者は、重篤な健康問題が発生する前に、かなり頻繁に昼間の眠気や 疲労を経験していると考えられます。
引用元:https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2012_01/Health_Problems_due_to_Long_Working_Ho
長時間労働による疲労は徐々に蓄積されます。その兆候は、「昼間に過度な眠気を感じる」「翌日に前日の疲れを持ち越す」などで現れます。
「疲労が回復出来ていない」「蓄積している」と感じたときは、すみやかに休息をとって対処しなければなりません。加えて、現在の働き方と生活の見直しが必要です。
疲労は放置して回復することはありません。そのままにしていると、重大な健康障害や事故によるケガなどをもたらす危険があります。
疲労が慢性的に蓄積していると、正常な判断ができないなど精神的な問題も起こり得ますので、軽く考えずに解消方法を考えましょう。
健康問題

長時間労働等の過重な労働負荷は、脳・心臓疾患を発症させる場合があり、 そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は労働災害として取り扱われて います。
引用元:https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2012_01/Health_Problems_due_to_Long_Working_Hours.pdf
時間外労働時間が増加するほど、脳・心臓疾患を発症するリスクが高まるとされます。
過去の時間外労働が一か月あたり80時間以上の労働者は、時間外労働をしない人に比べて心筋梗塞を発症するリスクが1.9倍に。長時間労働によって睡眠時間が1日5時間以下になると、6~8時間睡眠の人に比べて心筋梗塞発症リスクは2.5倍になるという研究報告がなされています。
また、長時間労働により精神疾患や自殺を引き起こす一因となることがあり深刻です。
それ以外にも、過敏性腸症候群や月経障害など長時間労働による健康被害は多岐に渡り、労働者に多大な影響を与えます。
長時間の過重労働は、重篤な健康被害をもたらすとして労災認定基準にも定められています。
若い頃はなんとかなった。そうなんです、年齢と共に健康面なども問題も多く出てくることが大きな問題となっています。飲食企業の多くは飲食店の固定概念から離れることができず、労働条件は厳しく、見返りが少ないのが大半です。
長期労働でも給与が良ければいいですし、給与が少なくてもプライベートの時間を確保できるならいいという方が多い中、なかなか飲食業働いた対価に対して平均、または以下の給与しかないのが実態です。私が経験する中で労働に対して納得のいく給与が貰えている人は見たことがありません。(もちろん上も見ればキリが有りませんが・・・。)
解消方法

ここからはどうやってその不安を取り除くかを説明したいと思います。
ただ、方法がいくつもあるわけではなく、且つありきたりな部分しかないことはご理解ください。
- 独立をする
独立にするのは勇気と資金が必要です。成功すれば収入は大きく変わり納得する部分は増えるのではないでしょうか。ただ、成功するとは限りません。
- 違う業種または条件の良い飲食企業に転職をする
業種を変えたり飲食企業で転職をし収入をあげていく方法もあります。ただ、いずれにしても知識や技術、資格といったところが自分の評価の後押しになるため、以前の職場での成功体験や成果などが必要となりますし、別業種になれば今までとは違うスキルの経験が必要になってきます。30代前の転職ならまた1から違う業種にでもいいかと思いますが、30代後半から40代の転職はそう簡単に行きません。即戦力採用ですし、この年齢において成果や経験がない人はまずは成功しないでしょう。
- キャリアアップを狙う
キャリアアップは上手に会社に貢献できるかがとても大事になります。成果ももちろん上げなければ評価には繋がりませんし、会社組織は基本的に上に行けばいくほどポストは少なくなります。1つの部長の席を何人もの人間に勝たなければ取れませんし、部長が退かないとまず席は生まれません。可能性が低いこととタイミングがとても必要になってきます。
- 現状維持
現状維持とは流れに身を任せる作戦です。仕方ないとして受け入れるのかどうか。めんどくさいと思ったりする方はこの選択肢をされるでしょう。意外と多くの方はここだと思います。抗ったところで評価は上がらないし、転職活動もめんどくさい、独立する勇気もない。なのでここ。になります。
この4つかと思います。
年齢層によっても判断が迷う部分でも有りますね。
まとめ
私なりのアドバイスを送るなら、勤めている企業で幹部層(店長職以上)を狙えないなら早期に転職をオススメします。人間は基本的に体力が落ちます。40代に20代の頃と同じパフォーマンスはできないのです。ただ、職位が変わらなければ求められている内容は変わりません。つまり20代の店長も40代の店長もやることは同じです。(きついと思いませんか?)
やり方はいくらでもあります。が何処かで自分を酷使しないと行けないときが必ず来ます。なぜなら客商売なので、波があるからです。今現在12月の忘年会シーズンの真っ只中です。今なんかもきっと酷使している方はいらっしゃるはずです。
そうならないために働いている会社で最大限の知識や技術を得て、必要あらば資格を取得し、何が起きてもいいようのに常に自分を磨いておく必要があります。本来は20代の頃からやっておくことが必要ですが、20代であまり考えられる人はいませんね。笑
ただ、この記事を読んで頂けてるのであれば何か自分に+になるような勉強を会社を利用してどんどんやりましょう。限られた時間を見つけて自分を成長させるような勉強をできると尚良いです。
40代からでは正直厳しいかも知れませんが、20代30代の人はまだまだ自分を伸ばす可能性が秘めてますし、成長した自分を受け入れてくれる手段はたくさんあります。可能性を広げれるように1日1日を大切にやっていけるようにしましょう!
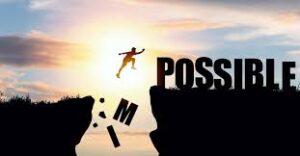
最後までお読み頂きましてありがとうございました!
Food Relation Management
キミタ(Blog name)