こんにちは、飲食店コンサルタントのキミタです!
皆さん大丈夫ですか!?昨今とても厳しくなりましたよね〜。これもご時世ですかね。
とは言え、集団で仕事をするには必ずつきまといますし、避けては通れないポイントです。ですが、安心してください!今日からあなたもコンプラインスマスターです!
それでは今回の記事はコンプライアンスについてのお話です!
コンプライアンスってなに?

コンプライアンスとは
コンプライアンス(compliance)という言葉の意味は「法令遵守」ですが、実際の社会生活の中でコンプライアンスが用いられる際に求められること、またコーポレートガバナンスやCSRとの違いについてご紹介します。

ん?法令遵守????
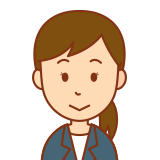
難しい言葉ですね。続きを見てみましょう
コンプライアンスの意味
コンプライアンス(compliance)とは、「法令遵守」のことをさし、企業や個人が法令や社会的ルールを守ることを意味しています。
コンプライアンスに求めらるのは「法令を守れば良い」というわけではなく、企業倫理や社会規範などに従い、公正・公平に業務を行うという意味も含まれています。

企業倫理?社会規範??
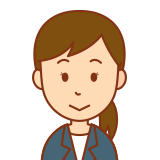
難しい言葉ばかりですね。
・企業倫理
企業倫理は、ビジネス活動の中で企業が遵守すべき道徳的価値や原則を指す概念です。
企業が利益を追求する過程で、法的要件を超えた倫理的責任を果たすための行動規範や判断の基準を提供します。具体的には、公正な取引、顧客のプライバシーの尊重、従業員の権利の保護、環境保護への取り組みなどが含まれます。
・社会規範
社会規範は、社会の一員としての人々の行動や態度を規定する、書かれていない「ルール」や「期待」を指します。
例えば「お年寄りや体の不自由な方がいたら、席を譲る」といった考え方は、社会規範の1つでしょう。
社会規範は、文化、伝統、教育、宗教などの多様な要因に基づいて形成され、個人が社会の一員として受け入れられるための行動や態度を示すガイドラインとして機能します。社会規範は、明示的な法律や規則とは異なり、遵守しなかった場合に法的な制裁が伴うわけではありません。しかし、社会規範を逸脱した行動をとると、社会的に大きな影響を与える恐れがあります。

なるほどな〜。なんとなくわかりましたよ。
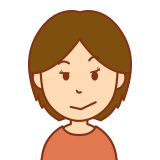
すごく簡単に言うと企業倫理と社会規範の内容を遵守すると言ったことで、それを逸脱した行為や行動などはコンプライアンス違反とみなされるということですね。
コンプライアンス違反の事例

ここでは、実際にあったコンプライアンス違反の事例を3つ紹介します。
①技術情報や顧客情報の持ち出しの事例
ソフトバンク社の元社員が、同社が5G化を検討している基地局などの情報が入ったファイルを持ち出した直後、楽天モバイル社に転職した事例があります。結果、不正競争防止法違反(営業秘密領得)罪として有罪判決がくだされました。
いかなる理由があっても、不正な手段により他社の営業秘密を取得してはなりません。
参考:5G情報持ち出し地裁判決、ソフトバンク元社員有罪|日本経済新聞
②下請法違反の事例
公正取引委員会によれば、下請け業者への買いたたきや下請け代金の減額などの下請法違反が、2022年度に指導・勧告した件数が8,671件(前年比+745件)あったと発表しています。
指導・勧告した措置件数では、製造業が37%、卸売・小売業が20%、情報通信業が13%という結果でした。
参考:下請法違反、過去最多の8671件 22年度に公取委|日本経済新聞
③ハラスメントの事例
広島市の消防局で、部下の職員4人に対し、日常的に「ジュースをおごれ」「お菓子を買ってこい」との発言や、部下の椅子を蹴って威圧するなどのハラスメントで、停職1カ月の懲戒処分の事例があります。
本人は「冗談のつもりだった」「パワハラに該当するとは知らなかった」と話しているそうですが、れっきとしたハラスメントとなります。
参考:部下に「ジュースおごれ」「お菓子買ってこい」消防局職員を停職処分|朝日新聞
これらすべてがコンプライアンス違反となったわけです。3番目なんてまだこんな事あるの?!って思うような事例ですよね。リアルです。笑
ではハラスメントという言葉が出ましたので。
ハラスメントとは!?

ハラスメントとは?定義は?
ハラスメントは「harassment」という英語で、「いじめ、嫌がらせ」という意味です。職場環境において、異なる権限や地位を持つ人物によって行われる不適切な言動や行為を指します。
近年、職場におけるいじめや嫌がらせによって、うつ病などの健康障害が労災認定される事案が増えています。人権侵害にもなることから、法的規制が強化されています。
しかしながら、ハラスメントを一律に定義することは簡単ではありません。被害者がハラスメントとして不快に受け止めるかどうかが重要なポイントとなりますが、言動が意図的であったかどうかは問われないからです。

コンプライアンスとハラスメントの違いはなんですか?
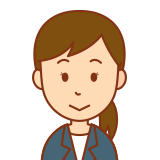
良い質問ですね!
ハラスメントとコンプライアンス違反の違い
ハラスメントもコンプライアンスも近年注目されるようになったため、日本では比較的新しい言葉です。そして、コンプライアンス違反とハラスメントはどちらもモラルやルールに反するものとして混同されがちです。あくまでハラスメントは、相手の意に反していじめや嫌がらせをすることであり、コンプライアンス違反は法令違反や社会規範に反する行為や事例を指すため、すべてのハラスメントが直ちにコンプライアンス違反に当てはまるわけではありません。そこでここからは、具体的なハラスメントとコンプライアンス違反の事例をご紹介します。
ハラスメントの事例
ハラスメントに該当する事例には、以下のようなものが該当します。
・ミーティングに一人だけ呼ばない
・他の従業員の前での長時間に及ぶ執拗な叱責
・人格を否定するような暴言
・退勤時間直前に大量の仕事を一人に押し付ける
・コピーやお茶くみなどの簡単な仕事しか与えない
・仕事をさせない
・飲み会や食事への参加の強要
・殴る、叩くなどの暴行
・体調不良での休みを認めず出勤を強制
・女性だからとスカートの着用を強要
・育児休業取得申請後に合理的理由のない人事異動
・休憩時間の電話番の強制
・介護のため時短勤務中の従業員に対して家族の悪口を言う
・独身を理由に昇格させない
コンプライアンス違反の事例
コンプライアンス違反に該当する事例は以下のようなものが含まれます。
・個人情報が含まれたデータを社外に持ち出す(情報漏洩)
・組織ぐるみでのハラスメントのもみ消し
・製品や会社の設備の私的利用
・サービス残業の強要(労働基準法違反)
・インターネット上の写真の無断商用使用(著作権の侵害)
・残業代目当ての自己判断の残業
・誇大広告
・長時間労働の強要による過労死
・製品テストの改ざん
・脱税
コンプライアンス違反では、従業員一人の問題であっても、それらの管理責任や対策、トラブル発覚後の適切な対応が求められます。
などが事例と上げられます。コンプライアンスとハラスメント混合しないように注意が必要ですね!
ハラスメントの種類
ハラスメントの種類は、当事者の関係や言動によって数十種類あるともいわれています。ここでは、代表的なハラスメントを紹介します。
セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメントは、性的な言動や行為によって、他の従業員が不快や恐怖を感じる状況を指します。例えば不適切なジョークや性的なコメント、不適切なタッチ、性的な関係の要求などが該当します。セクシャルハラスメントは、被害者に対する性別に基づく差別とも関連しています。
パワーハラスメント
パワーハラスメントは、上司や管理職などの立場のある人物が、自身の権力を濫用して他の従業員を脅迫したり、威圧したりする行為を指します。無理な残業や過度な圧力、公正な評価・昇進の妨害、人格的な攻撃などが含まれます。
モラルハラスメント
モラルハラスメントとは、他の従業員に対して道徳的な価値観や倫理に反する言動を行うことです。嫌がらせの意図的な無視や人格的な攻撃、陰口や中傷、プライバシーの侵害などが該当します。
アルコールハラスメント
アルコールハラスメントは、職場内でのアルコール摂取に伴って発生するハラスメントです。無理な飲酒の強要や、飲み会での嫌がらせ・暴力行為、飲酒による他の従業員への不適切な言動などが該当します。
マタニティハラスメント
マタニティハラスメントは、妊娠や出産に関連して女性が受けるハラスメントです。妊娠に対する差別的な扱いや、妊婦への過度な負荷のかかる業務の割り当て、妊婦の労働条件の不適切な変更などがあります。
セカンドハラスメント
セカンドハラスメントは、ハラスメントの被害者と加害者の間に立つ第三者が、被害者に対してさらなるハラスメントを行う行為を指します。被害者を助ける代わりにさらに攻撃する、被害者を信じない態度を取るなどが該当します。
リモートハラスメント
リモートハラスメントは、テレワークやリモートワークにおいて発生するハラスメントです。オンラインでの嫌がらせや侮辱、ビデオ会議での不適切なコメント・行動などが該当します。
ジェンダーハラスメント
ジェンダーハラスメントは、性別に基づいた差別やハラスメントを指します。性別に関連した侮辱的なコメントや差別的な待遇の他、女性の容姿や服装に関する不適切な評価なども該当します。
スモークハラスメント
スモークハラスメントは、喫煙者が他の従業員に対してタバコの煙を浴びせる行為を指します。被害者がタバコの煙を嫌がっているにも関わらず、それを無視して喫煙を続ける行為も含まれます。
テクノロジーハラスメント
テクノロジーハラスメントは、テクノロジーの使用やデジタルコミュニケーションの手段を悪用して行われるハラスメントです。電子メールやチャットでの嫌がらせや、オンラインプラットフォームでの誹謗中傷などが該当します。
スメルハラスメント
スメルハラスメントは、他の従業員が嫌な臭いにさらされることによって引き起こされるハラスメントです。個人の体臭や香水、食事の匂いなど、さまざまな要因によって発生します。スメルハラスメントは個人の感覚に依存するため、被害の大きさは人によって異なります。
リストラハラスメント
リストラハラスメントは、主に組織のリストラクチャリング(再構築)や人員削減の過程で生じるハラスメントです。企業が人員を削減する場合、その対象となる従業員に対して仕事を与えない、降格させる、配置を転換するなど、不当な扱いや圧力がかけられる状況を指します。

なんでもハラスメントになりそうですね…。。
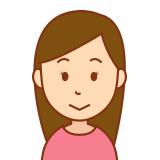
そうなんです。近年ではハラスメントの境界線がわからず具体的な指導や教育が行き届いていないという懸念点も生まれているぐらいです。
逆パワハラとは?
「逆パワハラ」とは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。
通常の「パワーハラスメント」は、上司から部下に対して、社内での優越的地位を背景に行われるというイメージがあります。
そのため、通常の「パワーハラスメント」とは「逆」のパワーハラスメントであると呼ばれているのです。
つまりハラスメントという言葉を上手く利用している人も中にはいる。ということも一つの認識となります。上司はハラスメントという言葉一つで普段の指示も躊躇してしまいます。
ハラスメントにならない正しい言動を理解する

ハラスメントの防止と対策① ~加害者にならないために
ここからは、「加害者にならないために」まずは、自身が加害者にならないためにどうすればよいかを考えていきましょう。
(1)自分の常識と相手の常識は異なることを強く認識する
①「自分が若い頃は普通だったこと」は、今は普通ではないかもしれない
企業内研修において近年トレンドとなっているテーマのひとつに、管理職対象のハラスメント防止研修があります。その研修の場で、必ず受講者から聞こえてくるのが「こんなちょっとした行動がハラスメントになるなんて、若い頃は普通だったのに!時代は変わったなぁ」「昔はよかったなぁ、変な気を使わなくて済んだから」という声です。
ハラスメント如何にかかわらず、自身の経験則からは考えられないことに対して、人が戸惑いをおぼえるのは、ごく自然なことといえます。
しかしながら、研修受講者の声にもある通り、時代は変わった(正確には変わり続けている)のです。組織の構成員がみな画一的な価値観をもつことが良しとされた時代は終わりました。世代間の価値観の違いのみならず、ジェンダーや国籍、宗教その他、これまでに過ごしてきた人生、育った環境によって、何を正しいと思うか、また何を嬉しいと感じ何を不快に感じるかは千差万別です。そしてそれらの多様な価値観・考え方のなかで、絶対的に正しいものはありません。
まずはそのことを強く認識し、「自分にとっての当たり前が相手にとって当たり前とは限らない」「自分の考え=正解、ではない」という事実を受け止めることが、加害者となってしまうリスクを抑えるための第一歩です。この事実を手帳の隅などよく目につくところに書き留めておくなど、自分の意識に浸透させるための工夫をすることもおすすめです。
②「だろう」判断から「かもしれない」判断へ
ハラスメントに限らないことですが、リスク管理が得意でない人の考え方の特徴に、何事も「だろう」で考えてしまう(本記事では『「だろう」判断』と呼びます)、というものがあります。
▼セルフチェック!次のような言葉をよく口にしていませんか?
-
「わざわざ説明しなくても(相手は)わかってくれているだろう」
-
「これぐらいのことは許されるだろう」
-
「後でフォローすればまぁどうにかなるだろう」
-
「ちょっとくらい適当でもまぁ大丈夫だろう」
「だろう」判断は、ポジティブシンキングといえなくもないですが、ハラスメント防止の観点からは、この考え方はとてもリスクが高いものです。
セルフチェックにあるような言葉をよく発しているなと感じた方は、「かもしれない」で考える(本記事では『「かもしれない」判断』と呼びます)よう心掛けましょう。「かもしれない」判断をすることで、相手との認識の相違を防ぐことができます。
▼「かもしれない」判断の例
-
「わかってくれているだろう」⇒「わかってくれていないかもしれない(⇒改めて確認しよう)」
-
「許されるだろう」⇒「許されないかもしれない(⇒あらかじめ相手に承諾を得ておこう)」
すなわち、ハラスメントにありがちな、「加害者側は、相手も合意のうえだと思っていた」「加害者側は、相手を傷つけるつもりはなかった」といった事態を防ぐことができます。「かもしれない」判断も、手帳などに書き留めておき自分の意識に浸透させることをおすすめします。
(2)相手に合わせたコミュニケーションをとる ~「悪平等」にしない
ハラスメントか否かの判断には、もちろん一定の客観的な判断基準も存在するものの、「相手がどう感じたか」が非常に重要なカギとなります。つまり、同じことに対してハラスメントと受け取る人と受け取らない人がいるということです。
組織で働くうえで「平等」という言葉は頻出しますが、「平等」と「公平」は異なります。たとえば、体の大きさや筋肉量を無視して全員同じ重さの荷物を運ぶなど、ひとりひとりの特性を無視して同じ扱いをすることは、「悪平等」であって「公平」ではありません。同じように、仕事の割り振り方やものごとの伝え方についても、相手を注意深く観察し、相手に合わせて変えることが必要です。
(3)相手を「指導」するときの注意点
パワハラは、上司・部下間に起こるもののみを指すわけではないとはいえ、やはり件数として多数を占めるのは、上司から部下に対するものです。なかでも、意識的にしろ無意識的にしろ、業務上必要な「指導」がエスカレートして「パワハラ」になってしまった、という事例は多くみられます。
パワハラと指導には、明確な境界線がないうえ、行為者がどういう意図で言ったのかは、パワハラの判定には関係ありません。そこで、上司側が、パワハラと指導の違いを正しく認識することが重要です。

指導を行う際には、上記も踏まえながら、以下の3つのポイントに留意しましょう。
- ①目的(相手のどのような成長を願って、どのような考え方や行動に対して指導するのか)を明確にする
- ②一方的に話すのではなく、相手に気づいてもらう(相手にも発言を促し、なるべく改善点は相手の口から出てくるように促す)
- ③相手の話もきき、お互いの信頼関係を増すことを心がけ、指導する側も努力する
また、上司は「上司である」というただそれだけで、自分の言動は自分で想像している以上に部下にとって影響力が高いということも認識しておきましょう。
https://www.insource.co.jp/contents/harassment-contents.html
まとめ
いかがでしたでしょうか?
なんとなくわかっているようでも言っちゃうんですよね〜。やっちゃうんですよね〜。私も笑
悪気もないし、なにも考えてないけど育った環境ですかね。笑
ただ、日々カスタマイズされてますし、本当に敏感になっているのはご時世ですね。冒頭でも言いましたが、多くの仲間や価値観の違う人々と仕事をするのは容易ではないんですよね。自分ファーストではなく相手を思いやる気持ち。それができればこんなのはなくなるんですよ。
一人の努力が明日の変化です!
頑張ってアップデートしてやっていきましょう!

最後まで読んで頂きありがとうございました!
Food Relation Management
キミタ(Blog name)
